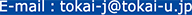2017年度 例会及び講演会発表要旨
●2017.5.12|Lipid management now and in the future
Dr. Jane Armitage
Clinical Trials and Epidemiology University of Oxford
Professor, Public Health Medicine, Honorary Consultant
Professor, Public Health Medicine, Honorary Consultant
司会:後藤信哉(内科学系循環器内科学)
数年程度の短期のランダム化比較試験が多く施行されている米国と異なり、英国では10年を超える長期の、かつ数万人を超えるランダム化比較試験が数多く施行されています。これらの試験を可能とするオックスフォード大学におけるランダム化比較試験管理方法の詳細について概説します。日本では高価なCROを使う試験を如何に安価に、かつ質を担保して学術的に行う方法があるのか、われわれは多くのことを学べると思います。現在進行中の試験についてもお話頂ける予定です。臨床家の先生が是非若手にも声をかけて頂き、世界のエビデンスがどのように生まれるかを学んで頂きたいと存じます。
●2017.5.12|インフルエンザウイルスの宿主への適応戦略
渡辺登喜子 先生
東京大学医科学研究所 感染・免疫部門 特任准教授
司会:中川草(基礎医学系分子生命科学)
インフルエンザは毎年冬になると流行し、乳幼児や高齢者を中心に多くの犠牲者を出し、社会的な問題となっています。また、2009年に出現した新型H1N1ウイルスのように、インフルエンザウイルスは数十年に一度世界的大流行(パンデミック)を引き起こし、甚大な被害をもたらします。さらに最近、H5N1亜型やH7N9亜型といった鳥インフルエンザウイルスが人に感染して重篤な症状を起こす例が多く報告されており、鳥インフルエンザウイルスによるパンデミックの危険性も懸念されています。インフルエンザウイルスの自然宿主はカモなどの野生の水禽です。水禽が保有しているインフルエンザウイルスが、自然宿主でない他の動物へと伝播することはまれであり、さらに伝播した先の動物間でインフルエンザウイルスの伝播は容易には起こりません。なぜならそこには、宿主の違いという大きな壁があるからです。しかし、ひとたびウイルスが、宿主の壁を乗り越え他の動物へと伝播し、さらにその動物間でも伝播できる能力を獲得すれば、瞬く間にウイルスは広がりパンデミックを引き起こす可能性が高くなります。我々は、鳥由来のインフルエンザウイルスが、どのようにヒトに適応していくのかを調べるために、これまでにパンデミックを引き起こしたインフルエンザウイルスや、ヒトから分離された鳥由来ウイルスを用いて、研究を進めています。また、インフルエンザウイルスの増殖メカニズムの全体像を分子レベルで理解するべく、インフルエンザウイルスの増殖に関わる宿主因子の同定および機能解析を行っています。本発表では、最近得られた研究結果をもとに、インフルエンザウイルスの宿主への適応戦略について概説します。
●2017.5.19|リンパ系腫瘍のmiRNA研究
田川博之 先生
秋田大学大学院医学系研究科 腫瘍制御内科系血液/・腎臓・膠原病内科学分野 講師
司会:幸谷愛(内科学系血液・腫瘍内科学)
がん細胞は、異常なストレスにさらされた正常細胞にゲノム構造異常かエピゲノム異常 またはその両者が生じ、「がん関連遺伝子」が発現異常を起こし、結果、細胞老化を克服し、クローナルな細胞増殖能を獲得した細胞であります。前世紀までは遺伝子異常により生じた翻訳蛋白の異常発現が注目されていました。しかし、今世紀に入ると「遺伝子-RNA-蛋白」といった転写-翻訳のセントラルドグマから外れたところで働くmiRNAの発がんへの関与もがんの病態に密接に関わることが示されました。私は2004年に悪性リンパ腫のゲノム構造異常の解析からmiRNAの発現異常を同定して以降、miRNAの発がん関与の研究をし続けています。一連の研究でわかって来たことは、miRNAは付加的な遺伝子異常のひとつではなく腫瘍化の本質なところに関与している、ということです。本講演会では、リンパ系腫腫瘍を対象として、腫瘍化の進展あるいは腫瘍細胞の生息環境の相違によってエピジェノミックに発現変動するmiRNAについてその発現変化が病態にどのように関与するのか、を中心に発表いたします。時間があれば治療標的分子としての意義などについても議論したいと考えています。
●2017.5.26|心臓に優しい麻酔を考える
平田直之 先生
秋田大学大学院医学系研究科 腫瘍制御内科系血液/・腎臓・膠原病内科学分野 講師
司会:鈴木利保(外科学系麻酔科学)
麻酔科医は患者の苦痛を取り除くという目的で様々な麻酔薬を使用しております。健常人であれば、麻酔による循環抑制は自動能調節により問題になることはほとんどないが、循環器合併症を有する高齢患者では、脳や心臓など酸素消費量の多い臓器において、循環抑制により虚血性傷害を引き起こす危険性があります。近年、高齢患者が増加している現状を鑑みれば、臓器保護を考慮し循環管理を行うことは麻酔科医の責務かと思います。今回、周術期の保護すべき臓器として、心臓に焦点を当て、日常臨床における循環管理について、基礎的なエビデンスや臨床研究をご提示いただきます。さらに、日常の麻酔前診察で心臓リスクをどのように評価すべきかをQ&A形式でご紹介し、心臓に優しい麻酔について考える内容をご講演いただきます。
●2017.5.26|蛋白をコードしない反復配列RNAの異常発現による膵発癌促進の分子機構解明とその臨床への応用
大塚基之 先生
東京大学大学院医学系研究科 器官病態内科学講座消化器内科学分野 講師
司会:幸谷愛(内科学系血液・腫瘍内科学)
microRNAをはじめとするノンコーディングRNAに関する研究は、国内外で一大研究分野として発展しているが、いまだに詳細な生物学的意義のわからないノンコーディングRNAも存在する。中でも反復配列RNAは特定の遺伝子座が無く配列が多様なため、通常の解析手法が適用しづらいという特色があるうえに、通常は強く転写が抑制されており、仮に転写されても転写長や配列が不均一で生物学的意義は乏しいと考えられていた。本研究では、このような反復配列RNAが、膵癌の前癌病態の時期から発現しており、それが細胞内分子環境を攪乱することでいわば「細胞内変異原」として機能し、発癌機構として極めて重大な役割を持つことを解明した。この結果は、細胞の癌化機構の解明や 予防医学をめざした臨床応用に向けた基盤となる可能性がある。また、我々は 通常の増幅法では正確な定量が難しい反復配列RNAの高感度定量法を開発し、膵癌あるいは膵癌の前癌病態の患者さんの血清でその量を測定することによる疾患囲い込みを試みた。この方法は、既存の腫瘍マーカーを超える感度・特異度を有しており、 現在 企業との連携でキット化を進めているところである。
本講演では、膵癌における反復配列RNAの異常発現にまつわる 基礎的・臨 床的な私たちの研究内容を御紹介させていただければ、と考えている。
●2017.5.31|蛋白をコードしない反復配列RNAの異常発現による膵発癌促進の分子機構解明とその臨床への応用
川口義弥 先生
京都大学 iPS細胞研究所 教授
司会:穂積勝人(基礎医学系生体防御学)
受精卵に始まる発生過程において、細胞は一瞬たりとも“孤立”せず、常に他細胞との接触を保ちながら、個々の細胞特性を獲得してゆく。そこでは、細胞分化と立体構築の変化が同時進行し、機能的構造単位たる組織構築が完成する。iPS細胞をはじめとする多能性幹細胞から機能的細胞を作製する研究の王道は、“発生現象を培養皿上で再現すること”である。たしかに、多くの研究は“受精卵から目的の細胞になるまでの多段階分化ステップを再現しようとしてはいるが、実際の発生過程に見られる立体構築の変化にはあまり注意が払われていない。本講演では、膵臓の発生・再生・がんにおける、細胞特性の変化(分化・脱分化・がん化)は必ずしも細胞自律的機構のみで制御されているのではなく、他細胞からの働きかけによる非自律的制御をも受けていることを示し、細胞分化制御における立体構築の変化の意義を考察する。
●2017.6.20|バイオイメージングに関わる学際的技術革新
宮脇敦史 先生
理化学研究所 脳科学総合研究センター光量子工学研究領域 チームリーダー
司会:永田栄一郎(内科学系神経内科学)
細胞の中を動き回る生体分子の挙動を追跡しながら、ふと、大洋を泳ぐクジラの群を想い起こす。クジラの回遊を人工衛星で追うアルゴスシステムのことである。背びれに電波発信器を装着したクジラを海に戻す時、なんとかクジラが自分の種の群に戻ってくれることをスタッフは願う。今でこそ小型化された発信器だが昔はこれが大きかった。やっかいなものをぶら下げた奴と、仲間から警戒され村八分にされてしまう危険があった。クジラの回遊が潮の流れや餌となる小魚の群とどう関わっているのか、種の異なるクジラの群の間にどのようなinteractionがあるのか。捕鯨の時代を超えて、人間は海の同胞の真の姿を理解しようと試みてきた。バイオイメージング技術において、電波発信器の代わりに活躍するのが蛍光性(発光性)プローブである。生体分子の特定部位にプローブをラベルし細胞内に帰してやれば、外界の刺激に伴って生体分子が踊ったり走ったりする様子を可視化できる。蛍光や発光の特性を活かせば様々な情報を抽出できる。今生物学はポストゲノム時代に突入したと言われる。ポストゲノムプロジェクトを云々するに、より実際的な意味において、細胞内シグナル伝達系を記述するための同時観測可能なパラメータをどんどん増やす試みが重要である。我々は、細胞の心をつかむためのスパイ分子を開発している。材料となるのは可視光を吸収あるいは放出するタンパク質、特に蛍光タンパク質(自ら発色団を形成して蛍光活性を獲得するタンパク質)である。近年の遺伝子導入技術の進歩のおかげで、蛍光タンパク質を利用したスパイ分子がますます活躍している。そうしたスパイ分子を活用して、動物の脳で起こる現象を深く、広く、細かく、そして速く、長く観る研究の実際を紹介したい。また、可視光と相互作用するタンパク質が、「光と生命体との相互作用」を巡る人類の発見から生まれ、それらの生物学的存在意義に関する我々の理解を超えて、ますます有用になっていく過程を広く考察してみたい。超ミクロ決死隊を結成し、微小管の上をジェットコースターのように滑走したり、核移行シグナルの旗を掲げてクロマチンのジャングルに潜り込んだりして細胞の中をクルージングする、そんなadventurousな遊び心をもちたいと思う。大切なのは科学の力を総動員することと、想像力をたくましくすること。そしてwhale watchingを楽しむような心のゆとりがserendipitousな発見を引き寄せるのだと信じている。
●2017.7.10|Current Issues in Patient-Centered Medicine
Dr. Gautam Deshpande
聖路加国際大学衛生大学院 副学長・教授
司会:高木敦司(内科学系総合内科学)
Dr.Deshpandeは、Penn State 大学医学部卒業後、UCSD、ハワイ大学で内科の修練の後、聖路加国際病院、米国大使館で勤務し、2015年からは聖路加国際大学公衆衛生大学院の教授に就任されています。日本に居住する外国人の医療ケアサービスへのアクセス、日本におけるプライマリケア、病院総合診療学、医学教育などを中心に研究、教育に従事されています。今回、患者中心の医療における課題について論じて講演をいただきます。
●2017.7.11|医学教育分野別評価に求められるアクティブ・ラーニング促進に向けたITC活用教育
R. ブルーヘルマンス 先生
東京医科大学 医学教育分野 准教授
司会:和泉俊一郎(専門診療学系産婦人科学)
東京医科大学は一昨年無事分野別評価を受審し良好な評価をいただき、更に次の評価に向けて、もうPDCAサイクルを回転させだしたところです。演者は医学教育学分野の教員として受審準備の中で、医学教育の中で求められているアクティブ・ラーニングを促進するためにICTを活用する努力をしてきました。この点を中心に解説いただきます。また、演者は医学教育学会「広報・情報基盤委員会」の一員として、情報基盤の開発にも長年かかわっており、東京医科大学で使っているオープンソースのMoodle(ムードル)とMahara (マハラ)を組み合わせてe-ポトフォリオシステムの構築を推奨しています。これらは、今後重要になる学習内容のデータベース化と学習評価のためのInstitutional Research(以下 IR)の基礎となります。これらの体験・展望についても講演いただきます。ちなみに、IR は欧米では全ての大学に設置されている部署で、東京医科大学において、今後取り組むべき重点項目の一つだそうで、本学においても取り組むべき案件です。これらの体験・展望についても講演いただきます。医療人を育てるミッションはすべての医大に共通です。
●2017.7.12|From melanoblast to melanoma : a stressed journey
Dr. Lionel Larue
Deputy Director of Normal and Pathological Signaling UNIT, Institut Curie
司会:木村穣(基礎医学系分子生命科学)
Melanoma is known as a radioresistant tumor. Melanoma is intra-tumorally highly heterogeneous due to its genetic instability and plasticity. This heterogeneity may explain, at least in part, the natural neo and acquired resistance of melanoma against therapies. In a two dimensional biological world, cells may switch from “proliferative” to “invasive”, and vice versa. Two transcription factors, Mitf and Brn2, may be of great importance in this switch. Brn2 is a POU transcription factor belonging to the Oct family. In vitro studies have shown that Brn2, as well as Mitf, is transcriptionally controlled by the Lef/β-catenin complex and indirectly controlled by Braf. Moreover, the level of Brn2 mRNA is controlled by miR-211, which is directly induced by Mitf. This switch would be modulated by the transcriptional activity of Brn2 on Mitf, but also on other crucial proteins of the melanocyte lineage such as Pax3. In human melanoma metastasis, it appears that melanoma cells are mainly Brn2-positive or Mitf-positive. However some cells express both or none of these two proteins. Here, we evaluated the importance of Brn2 during the establishment, the renewal and transformation of melanocytes using genetically modified mouse models, human genetics and cell lines. It appears that Brn2 is dispensable during the establishment and the renewal of melanocytes. The specific lack of Brn2 in the melanocyte lineage reveals that this protein is important for melanoma resistance against ionizing irradiation, which consequently results in the disappearance of melanocyte stem cells over time. Moreover, mouse melanoma models relevant for humans were generated, showing that Brn2 plays an important role during melanoma initiation and can be better used to improve melanoma therapies.
メラノサイトの発生からメラノーマまで分子生物学や発生工学を利用して幅広く研究している研究者で、一流雑誌に毎年のように論文が掲載されています。気さくな親日派ですので、気楽においでください。10年前にも講演したことがあります。(木村)
メラノサイトの発生からメラノーマまで分子生物学や発生工学を利用して幅広く研究している研究者で、一流雑誌に毎年のように論文が掲載されています。気さくな親日派ですので、気楽においでください。10年前にも講演したことがあります。(木村)
●2017.7.18|Noninvasive chromosome screening of human embryos by genome sequencing of embryo culture medium for in vitro fertilization
~受精胚の遺伝子情報を培養液から解析する~
~受精胚の遺伝子情報を培養液から解析する~
蔡立義 先生(講演は日本語で行います)
ART Center, The Hebei Maternity and Reproductive Medicine Hospital, Director
(注:東海大学医学博士です)
(注:東海大学医学博士です)
司会:和泉俊一郎(専門診療学系産婦人科学)
近年日本では、胎児染色体検査を母体血で行うことが可能となり、出生前検査における画期的な検査として話題になっている。さらに、体外受精卵の着床前検査を一部の施設において臨床研究が開始され、さらにスクリーニングとして行うことが検討されている。しかし着床前検査では受精卵の生検が必須でありその侵襲性が問題となる。このリスクを回避するために、我々は、体外受精卵の培養液を用いた着床前検査を開発した。その基礎的検討と共に、我々の症例を提示して、その手法(*)の将来性について論じたい。*Next-generation sequencing (NGS) using multiple annealing and looping-based amplification cycles (MALBAC) for whole-genome amplification (WGA)
●2017.7.28|全身性強皮症の病態・臨床・治療
竹原和彦 先生
金沢大学大学院 医学系研究科皮膚科学講座 教授
司会:馬渕智生(専門診療学系皮膚科学)
全身性強皮症は、皮膚、肺、食道、血管壁、心筋など、全身諸臓器の線維化病変を主徴とする疾患であるが、線維化所見に加えて免疫異常や血管障害もその病態に大きく関わっている。本講演では、まず全身性強皮症の臨床全般について紹介し、免疫異常として疾患特異的抗体とそれらと関係する臨床症状について概説したい。次いで、血管障害として毛細血管に見られる異常所見についても紹介する。さらに、TGF―βやCTGFなどのfibrosis に関与するcytokineの病因的関与について、我々のマウスモデルを用いた知見を中心に概説する。最後に、本症は難治性疾患とされているが、その治療法は近年飛躍的な進歩を遂げている。当教室が関与したものも含めて、新たな治療法についても紹介したい。
●2017.9.21|人工大腸がん幹細胞を用いたがん幹細胞の特性解析とがん治療への応用
小柳(青井)三千代 先生
神戸大学大学院医学研究科 内科系講座iPS細胞応用医学分野 特命助教
司会:中川草(基礎医学系分子生命科学)
ヒトのがん細胞は様々な細胞から構成されるヘテロな集団であり、このことが、がんの治療を難しくしているとされています。その中でも、がん幹細胞といわれる一部の細胞群は自己複製能、抗がん剤抵抗能、スフェア形成能、腫瘍形成能、多様性形成能を持ち、がんの再発転移、治療抵抗性の原因とされ、新規治療標的として注目されています。しかしながら、このがん幹細胞はがん組織中にほんのわずかにしか存在せず、またがん組織の入手自体も手術が行われる機関やタイミングの制約を受けることから、その起源や特性獲得の分子機構の解析が困難でした。そのような中で我々は2014年、大腸がんの細胞株に3つの因子(OCT3/4, SOX2, KLF4)を導入することでがん幹細胞の特性をもった細胞、すなわち人工大腸がん幹細胞を作製し、これを選択的に回収することに成功しました。(Oshima et al., 2014, PMID: 25006808) 。本手法はがん幹細胞研究に用いるサンプルの量的および時機的制約を解消するもので、がん幹細胞の特性の獲得や維持に係る分子機構の解明を通じて、がん幹細胞を標的とした診断、治療法の開発に役立つことが期待されています。今回の発表では、人工大腸がん幹細胞の遺伝子発現や維持培養法を検討することにより、がん幹細胞の特性の獲得や維持に関わる分子機構の一部を明らかにしたこと、(Ishida et al., 2017 in press)と、ヒト内在性レトロウイルスの発現解析を用いた今後の研究の展望についてお話したいと思います。
●2017.9.29|Clinical stages and prognostic factors of Amyotrophic lateral sclerosis in Chinese opulation
商慧芳 先生(Professor Hui-Fang Shang)
四川大学 华西医院神経内科 教授
四川大学 华西医院神経内科 教授
(Department of Neurology, West China Hospital, Sichuan University)
司会:秦野伸二(基礎医学系分子生命科学)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a fatal neurological disorder characterized by progressive upper and lower motor neurons degeneration. Up to date, there are no curable treatment, only with symptom treatment and limited disease-modifying treatment options. Better understanding of survival factors in ALS could help physicians and patients schedule therapeutic interventions. We conducted a study to evaluate the predictive factors associated with longer survival and construct prognostic nomogram in ALS patients. Through a large center-based cohort, longer survival time in ALS is associated with younger age at onset, slower rate of disease progression, higher BMI, CK, creatinine at baseline, lower HbA1c levels, and NIPPV treatment, after correction for other known factors. The nomogram proposed an effective way to predict the likelihood of longer survival and may be helpful for individual ALS patient to obtain additional information about disease progression and to receive appropriate treatment. These findings also can be helpful in the future clinical trials. Longitudinal collection of the variables of hematological factors of ALS patients from different ethnic groups will help to clarify whether and how they vary with the disease progression. We also have validated the King’s College staging system in a Chinese population, and shown this system is useful in clinical practice and clinical trials. The results of subset analysis indicate that patients with bulbar-onset progress faster in the early stage of ALS, and patients with onset-of-age older than 45 years have a rapidly progressive staging system. The effect of riluzole may be more prominent when it is initiated at early disease stage with long-term use. PEG and NIPPV treatments were essential when Stage 4B was reached.
●2017.10.13|唾液腺導管癌の臨床病理から治療戦略まで:多施設共同成果を踏まえて
長尾俊孝 先生
東京医科大学 人体病理学講座 教授
司会:大上研二(専門診療学系耳鼻咽喉科学)
唾液腺導管癌(SDC)は、組織学的に高異型度浸潤性乳管癌に類似した組織型を呈する極めて悪性度の高いまれな腫瘍で、de novoあるいは多形腺腫由来癌として発生する。SDCの標準治療は外科的切除であり、術後放射線治療が併用されることもあるが、それでも生存率が有意に改善しない。また、再発転移あるいは局所進行による切除不能症例に対しては、全身化学療法を試みることになるが、未だ標準的なレジメンは確立されていないのが現状である。一方、SDCではアンドロゲン受容体がほぼ全ての症例で陽性となり、HER2が約45%の症例で強発現するなど、本腫瘍は他の唾液腺癌にはない特異な性格を有することから、近年それら分子を標的とした治療症例の報告がなされるようになってきた。そこで我々は、約5年前に貴大学にもご協力を得て「SDC多施設共同研究プロジェクト」(全国7施設)を立ち上げ、現在に至るまでSDC患者に対しての最適な個別治療の確立、ひいては予後向上に向けて150例を超える大規模な症例の解析を多角的に行ってきた。本講演では、これら研究成果から明らかになってきたSDCの臨床病理像・分子病理像~最新の治療戦略について今後の展望を含めた解説を行う。
●2017.10.17|胸腺上皮細胞に発現する転写調節因子AIREによる自己寛容成立機構の解析
松本満 先生
徳島大学 先端酵素学研究所(免疫病態学分野) 教授
司会:穂積勝人(基礎医学系生体防御学)
原因不明の難病である自己免疫疾患の病態を明らかにすることは、免疫システムの根幹をなす「自己・非自己の識別機構」の作動原理を理解することに他ならない。AIREは胸腺の間質を構成する髄質上皮細胞(medullary thymic epithelial cell)に発現する転写因子であり、その機能障害によって自己免疫疾患を発症する遺伝病の原因遺伝子である。しかしながら、AIRE欠損に伴う自己免疫病態の発症メカニズムについては十分に解明されていない。AIRE欠損症は単一遺伝子の異常によって起きる病気であるため、AIRE遺伝子の改変操作によってマウスにヒトと同じ病態を再現することが可能である。私どもはAIRE遺伝子改変マウスを用いてAIREによる自己寛容成立機構について研究を行っている。
●2017.10.28|東海大学総合医学研究所「第13回研修会」
辻井潤一 先生
国立研究開発法人産業技術総合研究所 人工知能研究センター センター長
研修会は、研究成果の学内外への広報活動、若手研究者の育成、医科学分野に関連した他学部や研究機関との連携を目的に毎年開催しています。ライフ・イノベーション分野での”研究の峰”の構築を目指し、生命科学に関わる学内の教職員・学生などを対象に幅広く演題を公募して、各学部の若手研究者や大学院生を含めて100名以上が参加する中で、活発に議論が交わされ、若手に積極的な参加姿勢と良い刺激を与えています。今回は、国立研究開発法人 産業技術総合研究所 人工知能研究センター長の辻井潤一先生に特別講演をお願いしています。報告会終了後には、若手の発掘・育成の一環として、若手を中心としたポスターセッションを企画しています。学生や大学院生・博士研究員ら大凡50テーマを予定し、研究の独自性や内容を審査して、優れたポスター発表者young inverstigator award賞を投票で選出します。この試みは、若手研究者にとって東海大学各学部を横断する幅広い学術的交流の機会となり、研究の裾野を拡げる東海大学の活性化に繋がっていくと考えています。
●2017.11.16|Stem cells in spine surgery:the European experience
Gianluca Vadala, MD,PhD
Department of Orthopaedic and Trauma Surgery, Campus Bio-Medico University of Rome, Attending Surgeon
司会: 渡辺雅彦(外科学系整形外科学)
Degenerative disc disease (DDD) presents a large, unmet medical need which results in a disabling loss of mechanical function. Today, no efficient therapy is available. Chronic cases often receive surgery, which may lead to biomechanical problems and accelerated degeneration of adjacent segments. The partners including the RESPINE consortium have developed and studied stem cell-based, regenerative therapies with encouraging results in phase 1 and 2a trials. Patients exhibited rapid and progressive improvement of functional and pain indexes by 50% within 6 months and by 65% to 78% after 1 year with no side effects.
The lecture aims to present the RESPINE study. Moreover, preclinical evidences on alternative MSC transplantation methods will be also presented.
●2017.11.8|成体幹細胞の休眠性誘導機構 ~メラノサイトの幹細胞をモデルにした研究~
大沢匡毅 先生
岐阜大学 医学部再生工学講座生命機能分子設計分野 教授
司会:大塚正人(基礎医学系分子生命科学)
組織の幹細胞の大部分は休眠状態にある。しかし、組織が障害を受けると幹細胞は速やかに活性化し組織の再生を行う。このように必要に応じて休眠状態と活性化状態を可逆的に移行する幹細胞の可塑的な能力は、組織の恒常性を永続的に維持するために重要な役割を果たしていると考えられている。近年、幹細胞の制御機構を理解するための研究は目覚しい勢で進展してきたが、幹細胞が休眠性を獲得する仕組みや、休眠期から活性状態へ移行する仕組みについては、十分に理解されていない。我々は、このような幹細胞制御機構をするために、メラノサイトの幹細胞をモデル系として研究を行なっている。マウスでは、メラノサイトの制御に関わる分子の変異体は、体色異常という明瞭な表現型によって識別することが可能である。とりわけ、メラノサイトの幹細胞の制御に重要な働きを果たしている遺伝子の変異体は、若年性の白髪化という特徴的な表現型によって簡便に同定することができる。我々はこのようなメラノサイトの特性と、迅速に遺伝子改変マウスを作製する技術を組み合わせることにより、幹細胞の休眠性の制御に関与する遺伝子を同定することを目指している。本セミナーではこのような我々の取り組みを紹介するとともに、幹細胞制御機構について議論を深めたい。
●2017.11.8|薬物動態におけるトランスポーターの役割とその個人間変動
楠原洋之 先生
東京大学大学院 薬学系研究科分子薬物動態学 教授
司会:加川建弘(内科学系消化器内科学)
トランスポーターは、生体内において基質とする薬物の細胞膜透過を促進し、その基質選択性およびトランスポーター間の輸送活性の違いが、薬物の組織分布特性やクリアランス経路を決定する。トランスポーター機能の個人間変動要因として、①遺伝子多型に伴う遺伝的要因による輸送能力の個人差、②遺伝子多型以外の要因による人種差および③併用薬による機能阻害や発現誘導(薬物相互作用)が知られている。我々はin vitro試験に基づいて新規化合物の薬物動態特性や薬物相互作用ポテンシャルを予測する方法論の開発を行っている。また、ヒトにおける薬物動態研究として、従来の血中濃度の時間推移を対象とした薬物動態解析に加えて、PETイメージングを利用した組織分布も考慮した定量的解析、血漿中に存在する内在性基質に注目した薬物相互作用研究を展開している。本講演では、これまでの研究成果を紹介したい。
●2017.11.20|Lipid Metabolic Reprogramming Links Liver Fibrosis and Cancer
Hidekazu Tsukamoto, D.V.M., Ph.D., FAASLD
Professor, Department of Pathology
Director, Southern California Research Center for ALPD and Cirrhosis, University of Southern California
Director, Southern California Research Center for ALPD and Cirrhosis, University of Southern California
司会:稲垣豊(基盤診療学系再生医療科学)
Canonical Wnt pathway is critical in myofibroblastic activation of hepatic stellate cells (HSCs) in liver fibrosis. Yet, targets and functional significance of Wnt pathway in HSCs have not been identified. Our recent research identifies stearoyl-coA desaturase (SCD), which catalyzes formation of monounsaturated fatty acids as one of the β-catenin targets. β-catenin enhances SREBP-1c-induced Scd transcription by nearly 10-fold. SCD mediates activation of HSCs by a novel positive forward regulation of canonical Wnt pathway involving SCD2-ELAVL1-LRP5/6. Genetic ablation of Scd2 in HSCs prevents progression of liver fibrosis following repeated CCl4 hepatotoxicity or sustained cholestasis caused by ligation of the common bile duct in mice. The SCD2 deficiency in HSCs also prevents the development of progressive liver tumors initiated by DEN injection and promoted by consumption of alcohol-containing Western diet. This anti-tumor effect is associated with global lipid metabolic changes in tumor microenvironment, suggesting the importance of SCD expressed by activated HSCs in tumor-promoting lipid reprogramming.
●2017.11.21|メイドインジャパンの医学教育
富田愛子 先生
東海大学 客員准教授
司会:浦野哲哉(基礎医学系医学教育学)
我が国の医学部は2023年までに医学教育分野別評価(国際認証)を受けなければなりません。これを機に、世界標準をベースとする医学教育公的評価機関として日本医学教育評価機構が発足し、2017年3月、世界医学教育連盟から国際評価機関適格と認定されました。日本の医学教育はターニングポイントを迎えています。今までの当たり前は参考にして、これからの医療提供の形式を考え直す時期です。世界標準の医療提供を行うには医師の多様化が必要であり、医学の修得以外に人種、文化、言語、など様々な違いに対応できる柔軟性、社会性などを身につけるカリキュラムも重要と感じます。多民族国家のオーストラリアの医学教育と比較し、日本が取り入れられる、または日本が世界に発信できる教育法は何かを考えます。
●2017.11.30|“Replications, ridicule and a recluse” NgAgo and beyond
Dr. Gaetan Burgio
Group Leader at the John Curtin School of Medical Research,
and Head of the transgenesis core facility at the Australian Phenomics Facility,
the Australian National University, Canberra, Australia
and Head of the transgenesis core facility at the Australian Phenomics Facility,
the Australian National University, Canberra, Australia
司会:大塚正人(基礎医学系分子生命科学)
Novel precision genetic technologies such as CRISPR/Cas9 genome editing technology offer novel avenues to a better understanding the mechanisms of diseases. Using CRISPR/Cas9 we are able to precisely modify the mouse or the human genome by creating knockout or a specific single nucleotide change to enable the study of the function of the gene of interest. The generation of these models lies on the ability of Cas9 to create a double strand break in the DNA and the repair to occur via the error prone Non-Homologous End Joining (NHEJ) or the precise Homology direct Repair (HDR) mechanisms. A large body of work have been recently dedicated to either improve the technology to generate efficiently knockout or knock-in mouse models (point mutations, tags or floxed alleles) or to explore novel alternatives to Cas9 enzymes such as orthologs of Cas9 or others prokaryotes defence systems against viruses (Natronobacterium Argonaute (NgAgo)). This rapid pace of the technology development has generated a lot of excitement but also some disappointment over the lack of reproducibility of the experiments. I will discuss the latest developments and possible drawbacks in the field of gene editing technology.
●2017.12.12|Cardiac Function Improvement and Bone Marrow Response Outcome Analysis of the Randomized PERFECT Phase III Clinical Trial of Intramyocardial CD 133+ Application After Myocardial Infarction
Dr. Gustav Steinhoff
Rostock大学 心臓血管外科・教授
司会: 浅原孝之(基盤診療学系再生医療科学)
ロストック大学Gustav Steinhoff教授が、来日に合わせ東海大学を訪問されることになりました。バイパス手術時の血管再生細胞(骨髄由来CD133陽性細胞)移植治療を世界で始めて開始し、血管再生治療を世の中に広めた一人として、基礎医学から臨床医学まで幅広い研究を展開されています。最新の論文では、臨床治療成績のresponderとnon-responder間における分子・細胞解析研究を発表されています。
●2018.2.16|新規モデルマウスを用いた線維化メカニズム解析 ~慢性炎症の正体を探る~
芦田昇 先生
京都大学 医学部附属病院循環器内科 特定講師
司会:稲垣豊(基盤診療学系再生医療科学)
線維化は慢性炎症の結果として形成され、様々な、というよりも殆ど全ての疾患の病理学的な基盤を形成している。このため線維化の制御は喫緊の課題であるが、その分子学的メカニズムが実は殆ど解明されていないため、有効な抗線維化治療は未だ確立されていない。
メカニズム解析が困難であった大きな理由の一つとして、これまで適切な線維化モデル動物が存在していなかったことが挙げられる。最近我々は、皮膚および内臓の線維化と自己抗体の出現をきたすマウスを作製し、線維化・強皮症モデルマウスとして国際特許を取得した。現在それを用いた線維化のメカニズム解析や抗線維化薬の開発を行なっているが、そこから見えてきたのは漠然としか定義されてこなかった慢性炎症の正体である。
本講演では、心筋梗塞などにおける心筋リモデリングを例に線維化について概説するとともに、上記研究の最新内容について紹介する。炎症・線維化に対する概念を再考するきっかけとなれば幸いである。
●2018.3.23|Bリンパ球の運命決定機構
黒崎知博 先生
理化学研究所 統合生命科学研究センター グループディレクター
大阪大学 免疫学フロンティア研究センター(IFReC) 教授
大阪大学 免疫学フロンティア研究センター(IFReC) 教授
司会:穂積勝人(基礎医学系生体防御学)
液性免疫記憶は、外来抗原によって刺激されることによってはじめて成立する。これを支える細胞基盤としては、1)骨髄に存在し、長期間にわたって抗体を産生し続けるプラズマ細胞、2)再度の抗原刺激によって始めて活性化されるメモリーB細胞の、2種類の細胞から構成される。これら2種類の細胞は主として胚中心(GC)細胞から分化してくる。胚中心(GC)はB細胞レセプター(BCR)に変異が生じ、抗原に対して高親和性、低親和性と種々のGC B細胞が産生され、そこから、プラズマ・メモリーB細胞へと分化決定がなされる。この分化決定メカニズムに関して研究を進めてきたので、これらの成果について述べ、議論する。
●2018.3.23|粘液性軟部腫瘍の病理診断
吉田朗彦 先生
国立がん研究センター中央病院 病理科医員
司会:中村直哉(基盤診療学系病理診断学)
粘液性間質の豊富な間葉系腫瘍には数多くの腫瘍型が含まれるが、それぞれ治療方針が異なるため正確な病理診断が診療の要である。しかしながら決定的な免疫組織学的バイオマーカーが少なく、良性・悪性の誤りが生じやすいのが、このタイプの腫瘍の特徴であるともいえ、典型的な(H&E染色での)組織像についての十分な理解と、適切な鑑別診断の構築が欠かせない。この講演では粘液性軟部腫瘍について、主としてその病理組織学的特徴を詳述し、日常の病理診断現場における鑑別診断を含め、実践的な事項を解説する。また、一部の腫瘍型には近年特異的な遺伝子異常も発見されているから、それらの検出を診断ツールとして活用する方法についても触れる。講演でとりあげる腫瘍型は、筋内粘液腫、粘液性線維肉腫、粘液型脂肪肉腫、低悪性度線維粘液肉腫、骨外性粘液性軟骨肉腫、結節性筋膜炎などである。